道徳教育。日本で小・中学校時代を過ごした人はみんな、うけたことがありますよね。
戦前には、「修身」という授業があったということも、なんとなく聞いたことがあるような。
そういえば、他の国では、子供の道徳教育をどのように行っているのでしょうか。世界的な現状と日本の課題をまとめました。
世界の道徳教育ってどうなってるの?
海外では、日本のように「道徳」という独立した授業がある国は多くありません。代わりに、社会科や公民の授業、あるいは宗教の時間に「どうすれば社会でみんなと仲良く暮らしていけるか」を学ぶことが多いんです。
国や地域によって教える内容も全然違います。たとえば、アメリカの公立校では宗教的な話はしないけど、社会科の授業で市民としてのマナーやルールを教えます。ヨーロッパでは、みんなで社会を良くしていくための「市民教育」が主流。中国や韓国では、昔ながらの教えをしっかり伝える教育が続いています。
でも、最近はどの国もグローバル化が進んでいるので、違う文化を持つ人たちとどう共生していくか、世界平和のために何ができるかといったテーマが、道徳教育の大きなカギになっています。
| 国・地域 | 主な特徴 | 教え方・評価 | ユニークな点・違い |
|---|---|---|---|
| 日本 | 「思いやり」「努力」など、心の成長と他者への配慮を重視。 | 週1回の道徳授業。教科書を使い、テストではなく先生が文章で成長を評価。 | 同じ内容をみんなで学ぶ。思いやり・協調性を特に大切にする。 |
| アメリカ | 「正直」「責任感」「勇気」など、市民的価値と人格形成を重視。 | ディスカッションや体験的な授業が多い。学校ごとに内容や方法が異なる。 | 自主性・多様な考えを尊重。評価方法も学校で異なる。 |
| ドイツ | 「多様性」「合理的思考」など、一人ひとりの違いを尊重。 | 州ごとに違いあり。倫理や宗教、哲学も含めて授業を実施。自分で考え、議論する。 | 多様性の認め方を重視、宗教と分けて学ぶ。 |
| 中国 | 「良い習慣」「規律」「集団意識」「愛国心」に重点。道徳+法治や政治教育も。 | 国家基準の教科書。実生活や社会体験・ロールモデルを重視。 | 法治/政治教育、愛国主義・社会規範の強調が特徴的。 |
| イギリス | 「英国的価値観」「性格形成」「社会的・道徳的発展」を重視。 | SMSC(精神的・道徳的・社会的・文化的発展)をカリキュラム全体に統合。議論や体験学習中心。学校ごとの評価。 | Character educationフレームワークを推進。宗教教育と組み合わせ、多文化共生を強調。 |
| インド | 「誠実さ」「敬意」「共感」「伝統的価値観」に重点。国家教育政策で復活。 | 物語、グループ活動、文化イベントを通じた授業。記述評価や学校行事で育成。 | 宗教的・文化的ニュアンスが強く、一部の学校で独立教科。家庭・地域との連携を重視。 |
| フィンランド | 「倫理的思考」「世界観の形成」「共感と責任感」を重視。 | 世俗的倫理教育を宗教教育の代替として実施。議論中心の授業。教師の裁量が大きい。 | 教師の信頼が高く、個別化されたアプローチ。非宗教的な倫理教育の人気上昇。 |
| ブラジル | 「倫理」「市民性」「社会的責任」に重点。過去の政治的影響。 | Ethics and Citizenship Programを通じたプロジェクト学習。議論や実践活動。学校ごとの評価。 | 軍事政権時代の遺産から進化。価値教育の実験的アプローチ、多様な文化的文脈。 |
どこの国でも、自国の子供を「市民」として立派に育てるために、徳育をしているのが印象的ですね。
日本の道徳教育ってちょっと特殊?
日本は世界でも割と珍しく、小学校と中学校に、「道徳科」という授業がちゃんと独立してあるんです。しかも、教科書もあって、文部科学省のルールに沿って全国どこでも同じ内容を学べるようになっています。
日本以外では、中国や韓国などアジア圏には、同様に教科書を準備し、成績を付ける国があるようです。儒教の国だからでしょうか?
道徳は授業の中だけでなく、掃除や給食当番、学校行事といった日々の生活全体を通じて育むものだ、という考え方も日本の特徴です。ただ、2018年からは成績評価もつくようになったので、先生にとっては「子どもの心の成長をどう評価するか」という、かなり難しい課題が加わりました。
ちなみに、日本のように生徒が毎日自分の学校を掃除し、物を大切にする心や協力性、感謝の心などを教えるケースは非常に少数派です。
掃除を通して心を磨く文化は、仏教(禅)や神道の影響、武道の精神が根底にあるのかもしれません。

先生たちの負担が大変ってホント?
「特別の教科 道徳」として重要視されるようになった一方で、先生たちの負担がすごく増えているというのは強く実感するところ。
道徳を専門に教える先生はいないので、ほとんどのクラスでは担任の教師が担当します。
道徳の教科書は、一言で言えば読み物教材です。そこで展開される数々の出来事を通して、「あなたならどうするか」「人としてどうすべきなのか」ということを考えていくのです。
簡単に聞こえますが、これは先生にとっては大変な負担です。そもそも、授業をする自分の価値判断が正しいと、誰が言い切れるのでしょうか。先生によっては、道徳の教科書の内容に、異を唱えたい人もいるかもしれません。それでも、我々教師は、指導案に従って、「好ましいとされている道徳的価値」について、ひとこま50分のまとまった授業をせねばなりません。
また、大学で道徳教育の授業をしっかり学ぶ機会が少ないことも、この負担感の背景にあります。授業の「正解」がない中で、子どもたち一人ひとりの意見を尊重しながら進めるには、高いスキルが求められるからです。
教育学部などでは、道徳に関する授業が行われるところも多くなってきているようですが、他学部で教員免許状を取得した場合には、現場に出て初めて実践的な道徳の授業をしたという人も、決して少なくはないでしょう。
さらに、大変なのは「道徳の評価」です。ただでさえ忙しいのに、授業の準備に追われつつ、目に見えない子どもの心の成長をどう評価するかに頭を悩ませる先生が多く、負担感は大変強い。テストなどを行うわけではなく、授業観察と、1年間の変化を総合して文章表記で成績を付けるわけですから、その苦労は並大抵ではありません。
実際の「道徳の教科書」はこちら↓
これからの道徳教育、どうしたらいい?
この問題を解決するために、いくつかの改善策をまとめてみました。
- 先生たちをしっかり育てる:大学の教員養成課程で道徳の指導方法を充実させていくことが大切です。実践的な授業の仕組みを知ることができれば、教壇に立つやいなや道徳の授業をすることになって途方に暮れることも少なくなるかもしれません。
- 専門の先生やサポート体制を:有効な策としては、道徳教育のプロの先生を置くことです。専門の先生を置くことで、クラスによって道徳の授業で習得すべき価値観が揺れてしまうことも防げます。複数の先生で分担する仕組みがあれば、先生たちの負担も軽くなります。たとえば、学年の教師で担当する単元を決めて、その単元に関しては責任を持って道徳的価値について教えるという方法をとれば、クラス間格差は小さくなるうえに、年間で準備する指導案の数も少なくできます。
- 新しい教材やIT技術の活用:動画やシミュレーションなど、子どもたちが面白く学べるような教材が増えれば、授業の質も上がり、準備の負担も減るはずです。現在教科書として配布されている教材は、価値判断を問う教材としては弱い部分があることも否めません。読めば子供が模範解答をつらつらと答えられる作りになっているのも問題です。道徳的判断を身につけるために、周囲と積極的に関わったり、動画を通して興味を失わずに考え続けられる教材の開発が期待されます。
- 評価方法を見直す:「評価をつける」というプレッシャーをなくすためにできることを、「道徳の教科化」を導入した文科省にはよく考えてもらいたいですね。子どもの成長を文章記録するということがどれだけ大変で、かつ、公平性を欠くものであるかということは、議論の余地があると思います。もっと柔軟な評価方法、あるいは評価ではない形に変えていくことも必要でしょう。

おわりに
日本を訪れた外国人が、日本人の寛容さや優しさ、丁寧さを褒めることは少なくありません。こうした国民性は、古来から大切にされてきた「和の心」が背景にあると考えられます。そして、その価値観を次世代へ伝える手段の一つが、学校教育、特に道徳教育です。
道徳教育は学校の中だけで完結するものではなく、家庭や地域全体で子どもを育むものです。昔に比べると、かかわりが少なくなったとはいえ、近所のおじさんおばさんのふるまいを見て子供は成長し、その声かけで正しい価値判断を獲得しているのです。
みんなで協力して、グローバルな時代に合った新しい価値観を学べる道徳教育を目指していくことが、これからはもっと大切になりそうですね。
中学3年生の4月にやっておくこと→こちら
中学3年生の5月にやっておくこと→こちら
中学3年生の6月にやっておくこと→こちら


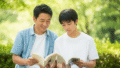
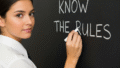
コメント