Xで、ブログの導線確保を狙っているため、
毎日のように、いそいそと掃き溜めのような場所に出掛けている。
今、わしがぶら下がる相手を物色している界隈では、
『教師は社会経験がなく、常識がない』論争がアツい。
そうだそうだという、教師でない輩。
そんなわけねえだろという、教師連中。
なんでこんなにも熱く、不毛な論争を繰り広げているのか。
わしから見ると、ただの時間の無駄に思えるけれど、
輩たちからすれば、
論争している時こそ、「生きている証」
わしも少し考えてみたのだが、
本当に教師は「社会性」がないのだろうか?
輩たちは言う。
『他業種を経験したことがないから、
生まれてこの方、学校から出たことがないだろ。』
そりゃ、一理あるな。
でもさ、警察官から教師に転身した人が言ってたけど、
圧倒的に教師の方が大変だってよ。
捜査権限も逮捕権限もないのに、
生徒指導案件が
エグすぎるってさ。
生徒指導のことはマジエグだから今日は書かないけど、
教師が普段やっていることをほんの一部だけ
取り出して整理してみた。
①プレゼン(=授業)
35人の顧客(=生徒)の前で、日々、プレゼンに励む。少しでもつまらなかったり、わかりづらかったりすると、速攻で居眠りなさったり、お絵描きなさったり、おしゃべりなさったりするので、片時も気が抜けない。
効果的な資料を提示し、パワポや動画を使いながら、できるだけポイントを突いてお話し申し上げても、大抵の場合、その場では簡単に頷かれるものの、次の機会には前回までの話を忘れてしまわれる。
こちらのプレゼンがお気に召さなければ、「競合他教科の〇〇先生の方が面白い」と、不名誉な評価を下されかねないため、毎回が真剣勝負である。
時にはおもちゃ(=iPad)で遊んでいただき、ワークシートに手書きでメモをお取りいただくなど、プレゼンには様々なバリエーションが必要なため、連日の超過業務の大半は、やはりプレゼンが占めていると言っても過言ではない。
②カウンセリング(=相談業務)
35人の顧客の皆様は、いつもいつも、穏やかでいらっしゃるわけではない。時にはイライラされたり、顧客同士の小競り合いがおこったり、心をお病みになってシクシクとお泣きになったりする。
そういう時には、カウンセラーの出番である。小さなカウンセリングでいい場合は、プレゼンとプレゼンの合間の10分休憩を使う。
顧客ががっつりサポートを要求するときは、お食事後の昼休憩を使ったり、お帰りになる前の時間を使ったりして、こまめなサポート体制を敷いている。
シクシクタイプには、ひたすら傾聴。おうむ返しを多用しながら、こちらがアドバイスをするというより、ご自身で答えに辿り着いていただくのが最善の道。言語化の苦手な顧客が相手だと、思わぬ時間を食うこともしばしばである。しかしここで手を抜かずにカウンセリングをしておくと、2年くらい経たあとで、突然の謝意を受けることがある。
顧客同士のいざこざの場合は、丁寧な聞き取り、迅速な対応、被害者の救済、加害者の引き離しなど、緊急対応能力が問われる。
また、顧客につながる大顧客様(=保護者)との連絡調整能力も欠かせない。場合によっては、顧客対応のみならず大顧客顧客対応を発動せねばならぬ時もあり、心労は計り知れない。
③マネージメント(=学級経営)
35人の顧客を一つの狭い箱に収容するための具体的方策を、一人のマネージャーが創意工夫で考え、実践する。マネージメントのための指南書を、大抵の若手は、相当数自腹で買っているはずである。
顧客の皆様は、たいそうわがままである。少しでも、その狭い箱の居心地が悪いと、顧客に連なる『大顧客様(=保護者)』に言いつけることによって快適さを担保しようとなさる。
朝の連絡に始まり、お食事の準備からご帰宅前のご機嫌伺いに至るまで、居心地の良さを提供することが、マネージメント業務の最大の使命である。
少しでも手を抜くと、「 I・JI・ME 」が勃発するなど、細心の注意と目配りが必要となる。
④ファシリテーション(=連絡調整・合意形成能力)
顧客の生活はマネージメント業務(=学級経営)によりがっちり守られているが、場合によっては「提供されるだけじゃつまらない」という気まぐれが生まれることもある。
そういう時には、顧客自らが、『狭い箱の運営方法を決めている』という気持ちにさせて、満足感を得てもらう必要が生じる。
狭い箱の会(=学級会)を開き、自分たちが何をしたいのか、てんでバラバラに話し合う。時には意見が真っ向から対立することもあり、間に入ってファシリテートすることが必須業務となる。
こちらを取ればあちらが立たず、的な空回りの議論を、それとは見えぬ力技でまとめ上げる。『自分たちの力で何かを生み出したのだ』という達成感に結びつけるために、時にはロビー活動をも辞さぬ構え。
裏で暗躍し、事前にある程度了解を取り付けておくことも、ファシリテーターの重要な任務の一つなのである。
ここでもしも、シクシクお泣きになる顧客が現れた場合は、②カウンセリングに戻る。
⑤ドキュメンテーション(=文書作成)
膨大な、事務・事務・事務。文書作成業務。
狭い箱のお便り(=学級通信)作成に始まり、各種アンケートの集計と分析、道徳評価(顧客一人一人に応じた文章表記)、指導要録作成、全国学力テストの検証報告、など、連日、書くことが山盛りである。
運が悪いと警察に、アオハルでハメを外し過ぎた卒業生の照会状を書かされることもある。(これ、クッソめんどい。)
不登校が出たとなれば報告文書、嫌がらせがあったといえば報告文書、児童相談所から連絡があったといえば報告文書、小中連携会議があったといえば報告文書。
何よりもイラつくのは、これらの報告文書を「誰も読まない」ということである。
なんのために書いているのか????
この、弱小ブログの方が、まだ読まれる率高いと思う。
⑥カスタマーサポート
顧客につながる「大顧客様(=保護者)」のご機嫌を損ねると、大変なことになるので、カスタマーサポートセンターは、ほぼ年中無休である。
夜遅い時間も、休日も、呼ばれればいつでも駆けつけます。もちろん、玄関先までお伺いいたします。最近では、遅い時刻は電話が繋がらないことも多いので、メールによるご相談も受け付けております。
顧客がお休みされる時にご連絡いただくためのメールには、連日、「誰それと喧嘩した」「誰それが嫌がらせする」「誰それが気に食わない」「宿題なんですか?」「時間割教えてください」など、さまざまなクレームお問い合わせが寄せられるので、カスタマーサポートセンターから折り返しお電話を差し上げる。
このサポートを放置すると、大顧客様が突如学校に現れ、校長室で暴れるという大立ち回りに発展しかねないので、細心の注意を払って、複数対応するのが基本である。
時には優しく、時には寄り添い、時には毅然と、だがしかし、あくまでも大顧客様のために、我々カスタマーサポーターは、日々受け応えの洗練に精進している。
⑦イベントプランナー
どでかいライブイベントが、年に複数回あるのが我々の仕事である。録画でよければ何度も取り直しもできようが、なにしろ、全てライブなのである。顧客が達成感を感じつつ、安全に「激」配慮して、一瞬のライブを演出する。観客も渾然一体となって、ライブをとことん楽しむ。そのために我々は何ヶ月も前から動いている。
例えば大きいものでいえば体育祭ライブ。10月開催なら7月あたりから、5月開催なら前年度末から顧客の訓練に入らなければ、ライブの目玉である応援合戦などは到底仕上がらない。
並行して、我々のイベント進行会議も開かれる。道具の準備や放送機器の準備、ライブ演奏(=吹奏楽)の手配など、やるべきことは多岐にわたる。ライブ会場設営は何日も前から周到に行われ、出演者である顧客がライブ当日に緊張して失敗しないよう、リハーサルも余念がない。
顧客の皆様は若さ溢れるご年齢ゆえ、多少、外での活動が長引こうとも、元気がいい。場合によっては「膝すりむいた」「足が痛い」と理由をつけて家にお帰りいただくことも可能である。
だが我々年齢を重ねたスタッフ一同にはもちろん休みなどは皆無だ。連日のイベント準備ですっかり干上がって、顔がげっそりやつれ、顧客から「レーズン」とあだ名を付けられたイベントスタッフがいた。かわいそうに……言うたるなや!…ワロタけど。
さあ、どうだ。これでも教師は社会性がないのか??
聞くところによると、外の世界では、
これらが「専門職」として細分化しているというではないか。
うちらのこと社会性がないって言ってるそこのおっさん。
学校現場に来てみ?
間違いなく、ソッコーで病むから。
1日目から、顧客のニヤニヤ笑いと目配せでやられるで?
腹立てて、「こら〜!」いうたら
すぐ「パワハラ」って言われるからな。
ニコニコしながらも、決して叱らず舐められず、
馬鹿にされずに生徒を動かす術は
一般人には到底真似できない職人芸なのだよ。
結論。
ここは「社会」ではない。
ガチモンの「戦場」なのである。
我々は、丸腰の兵隊なのである。
「社会人論争」とか、しゃらくせえ。
今日も、抗うつ剤をそっと仕込んで
戦場に出かけるのみ。
合掌。


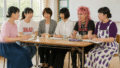

コメント